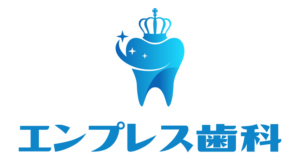子どものむし歯は、親の責任です
──エンプレス歯科が伝えたい、本当の意味での「予防」とは──
「うちの子、またむし歯ができちゃって……」
診療室で、そんな声を聞くことがあります。
一生懸命に歯みがきをさせている親御さんほど、そう言いながら申し訳なさそうに笑う。
でも、私たち歯科医は責めたいわけではありません。
むしろ、そこで一度“何が原因なのか”を一緒に考えてほしいのです。
■ 子どものむし歯、その多くは“食習慣”がつくる
むし歯の発生には、細菌・糖分・時間の3要素が関わります。
このうち、家庭で最もコントロールできるのは「糖分を与える頻度」です。
診療のとき、私はよくこうお伝えします。
「家にジュースやお菓子を常備しないでください。おやつの時間を決めて与えるだけで、むし歯はぐっと減ります」
すると、多くの親御さんがうなずきながら、横にいる子どもにこう言います。
「チョコばっかり食べたらダメだよ」
そのあとで、ため息まじりにこう続くこともあります。
「でも、子どもがねだるからつい買ってしまって……」
ここが、家庭での分かれ道です。
子どもは自分で買い物に行けません。
お菓子もジュースも、すべて“与える側”の判断で子どもの口に入ります。
つまり、子どもの食習慣をつくっているのは親。
結果的に、むし歯をつくっているのも親なんです。
■ 厳しいようで、一番優しい言葉
「子どものむし歯は親の責任です」
この言葉を聞くと、少し胸がチクッとするかもしれません。
けれど、それは責めるためではなく、“守る力”を持っているのは親だからこそ。
子どもは「甘い=ごほうび」「ジュース=うれしいこと」と学びます。
でもそれを“健康と引き換え”にしてしまったら、親として本末転倒です。
お菓子をゼロにする必要はありません。
量とタイミングを管理する。
ダラダラ食べを防ぐだけで、口の中のpHが回復し、再石灰化(歯の修復作用)が働きます。
これは科学的にも証明されています(J Dent Res. 2022;101(4):451–459)。
■ 仕上げみがき、たった5分の“未来投資”
ここからは、少し厳しい話です。
仕上げの歯みがきをしていない親御さんは、思っている以上に多い。
「忙しいから」「嫌がるから」「自分でできるようにしたいから」——。
でも、本当にそれでいいのでしょうか。
私は二児の父です。
夜、どんなに疲れていても、子どもの仕上げみがきをサボることはありません。
実際に計ってみると、1人あたり2分。
2人で5分弱。
テレビのCMを2本分見る時間です。
この5分で、子どもの歯の寿命が何年も変わる。
そう考えれば、迷う理由はありません。
■ 「嫌がるからやらない」では、習慣は育たない
確かに、小さい子は歯みがきを嫌がります。
口を開けない、泣く、逃げる。
私も経験があります。
でも、そこを“叱らずに乗り越える”のが大事なんです。
子どもが泣いても、親が冷静に続ける。
「終わったら絵本読もう」「数を数えて終わろう」といった声かけで、少しずつ慣れていきます。
最初のうちは大変でも、これが“未来の歯医者嫌いを防ぐ第一歩”になります。
■ 歯医者を「怖い場所」にしないでほしい
もう一つ、よくあるケースがあります。
診療室で親御さんが「痛いことしてもらうよ」「麻酔なしでやってもらうからね」と言う場面です。
それを聞いた瞬間、子どもの顔がこわばります。
逆に、「何もしないよ」と言っておきながら治療が始まると、子どもは“裏切られた”と感じます。
これは、信頼関係を失う最大のきっかけです。
歯医者は、痛みを与える場所ではなく、痛みを取り除く場所。
私たちは、麻酔や鎮静を含めて痛みのコントロールを徹底しています。
親御さんには、どうか「怖くない場所」として見せてあげてほしい。
「今日は歯をきれいにしてもらおうね」
それだけで、子どもの気持ちは全然違います。
■ 治療をスムーズに進めるために:母子分離のすすめ
小児歯科では、治療時に親子を一時的に離す「母子分離」が有効です。
これは“親を排除する”ことではなく、“子どもに自立心を持たせる”ステップです。
親の前では甘えてしまう子も、いざ1人になると案外しっかりできるものです。
終わったあと、「がんばったね」と褒めてあげるだけで十分。
歯医者への信頼と達成感が育ちます。
どうしても心配な場合は、治療後に説明を受けるスタイルをとればOK。
親御さんも安心できます。
■ 親が変われば、子どもの歯は変わる
子どものむし歯は、家庭の習慣の鏡です。
お菓子を“特別な日に食べるもの”とするか、“常に家にあるもの”とするかで、むし歯の発生率は大きく変わります。
研究でも、常時間食をする子どもは、1日2回までのおやつに制限している子の約3倍むし歯が多いと報告されています(Pediatr Dent. 2020;42(3):201–209)。
親が食環境を整え、仕上げみがきを習慣にし、歯医者との関係をポジティブに保てば、子どものむし歯はほぼ防げます。
つまり、治療ではなく習慣が子どもの歯を救うということです。
■ 親の5分が、子どもの10年を変える
ここまで少し厳しい話をしてきましたが、根底にあるのは「子どもを守りたい」という願いです。
むし歯は遺伝ではなく、習慣の病気。
親が変われば、結果は必ず変わります。
歯ブラシを持つその5分。
ジュースを買う前の5秒の判断。
それが、10年後の子どもの笑顔を決めます。
■ 最後に、エンプレス歯科からのメッセージ
子どものむし歯予防は、親御さんの日々の努力と、歯医者との信頼関係の上に成り立ちます。
私たちは“叱るため”ではなく、“支えるため”にいます。
歯医者を怖い場所ではなく、「一緒に育てる場所」に変えましょう。
仕上げみがきも、おやつの管理も、最初の一歩は小さくて構いません。
でも、続けることが一番の愛情です。
親が変われば、子どもも変わる。
それが、むし歯ゼロの未来をつくる最初の一歩です。